EVENTS
IMU(慣性計測装置)の知識や技術の普及促進を狙いにした当社のセミナーで、第50回を迎えた「MEMSモーションコントロール研究会」が6月、八戸第二工場で行われました。 第50回の節目に合わせて、ジャイロ営業担当の木下哲一理事にこれまでの経緯や今後の展望を聞きました。
木下哲一理事:
一つの節目にたどりつき、感無量の思いです。故・熊谷秀夫さん(2024年逝去、元専務)が発起人となり、第1回を開催したのが2014年3月。 その後、コロナ禍においては現地開催ができず、オンラインで参加者をつないで会を継続したことなど、大変な時期も思い出されます。
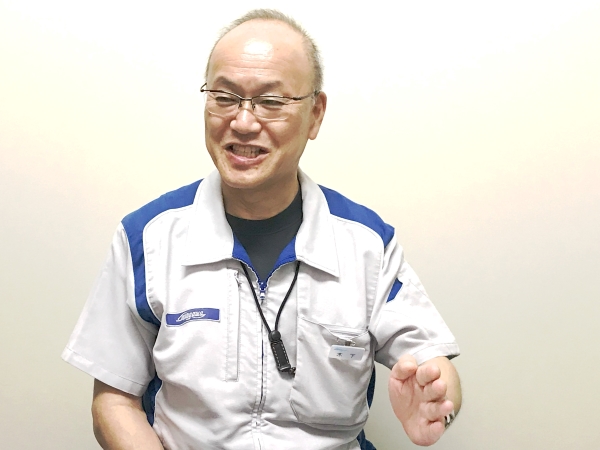
―研究会が発足した背景を教えてください
木下:
現在では非常に需要が高まっているジャイロですが、日本では教育の機会が少ない状況にありました。お客様がどのように活用するかを考えるきっかけづくりにもなればと、商業的な要素を排除し、アカデミックな内容に特化した講座を作ろうと考えました。タイミングよく、産業技術総合研究所(産総研)から、IMUの評価ツールである「3軸6自由度振動台」を購入した時期でもあり、こちらの実演紹介も兼ねたセミナーを企画しました。
基本的なフレームは50回を迎えても変わらず、ジャイロを学び、各社のアプリケーションに落とし込む中で、あんなことにも、こんなことにも使えるね、という気づきや販路が生まれています。セミナーの内容も回を増すごとに充実し、各社の事例を紹介し合い、参考にしていく機会にもなっています。
―11年余、50回にわたり続けられた秘訣は
木下:
ジャイロの基礎や応用を学ぶ中で、ともすればブラックボックスのような慣性演算の中身まで詳細に説明したり、疑問に感じていることを弊社のエンジニアに直接聞くことができたりの点も好評を博しています。我々は「IMUをもっと手軽に、もっと身近に、さまざまな用途に活用してもらいたい」の思いの下、他社は公開しないであろう技術情報やメソッドも惜しみなく伝授しています。
―当社のジャイロ関連の拠点は青森県八戸市にあります
木下:
IMUなどジャイロ製品の開発・製造拠点は青森県八戸市で、研究会も現地開催を基本としています。アカデミックな学びとともに、八戸の風土を体験できる機会として、口コミで評判が広がりました。
人気が出ても、毎回の定員は、相互にコミュニケーションがとれる少人数(現行12人前後)体制としています。セミナーでは、セッション後の懇親会もプログラムの一環としています。
親睦を深めながら、講義の内容に対する質問や、ジャイロを扱う中で確認したいことなどを、ざっくばらんに聞くことができる場としています。
こうしたダイレクトコネクションから進展した引き合いも少なくありません。各自が学ばれたこと、気づかれたことを自社へ持ち帰ってもらい、進展させる形で再び八戸へ来訪してもらえると大変うれしいです。

―節目に合わせて新製品「TAG320」もできました
木下:
MEMS IMUは2009年を初代とし、第4世代まで進化しました。量産に耐えうる製品ができたのはコロナ明けの「TAG310」です。
以前の製品は大きすぎで、機能も欲張りすぎた感があります。そうこうしている間に、市場で求められる精度は向上しています。
当社は今回、内蔵センサを刷新し、「TAG310」と外観・サイズは同じながらも、より低価格を実現した「普及モデル」と、より精度を高めた「高精度モデル」から成る「TAG320」を誕生させました。

―当社のジャイロ事業の経緯と今後に向けて
木下:
ジャイロは、当社の歩みや創業者である萩本博市氏の想いと非常に結びつきが深い製品です。
当社には、創業時からジャイロや慣性計測装置に関わってきたノウハウがあり、これらをもっと世の中の技術者に上手に使ってもらいたい。
ジャイロの使い勝手や特徴を理解してもらってこそ、さまざまな用途で有効に活用いただけると考えています。
ジャイロは当社のセグメント別の売上で見れば、現状は数パーセントですが、民間航空機のように2ケタ台を目指したい。
TAG320は海外市場も視野に入れています。数量ベースでは3年後に現状(TAG310比)の3倍、2030年以降は5倍以上を目指します。

――冒頭、大変だった時期もあったと
木下:
コロナ禍に起こった半導体製造メーカーの火災は大きな出来事でした。MEMSジャイロの重要部品であるASICの供給が途絶え、大変な思いをしました。
2020年から21年にかけての大きな転機です。
足りない部材をどうするか。
事業の継続が危ぶまれる中、限られた在庫部品を有効に使うため、採算性の低いカーナビ分野から撤退し、将来事業で期待が持てるIMUに集中投下する選択を決めました。
直近では引き合いが多かった農業機械や建設機械用途に注力し、開発を進めました。その結果、それまでIMU事業は赤字続きでしたが、20年には収益性が高まり黒字に転じました。
逆境下にあっても、知恵と工夫を出すことでチャンスに変えることができたのです。
――まさにピンチはチャンスですね
木下:
コロナ禍では、訪問や対面の営業活動や研究開発ができない中、新たな手法やツールを取り入れていく期間にもなりました。
研究会をオンラインで実施したり、PR動画を作ってみたり、従前にはないやり方を模索しました。
MEMS関連の単独のWEBサイトを全面的にリニューアルしたり、メルマガを配信したりしました。
社内では後に民航やFGビーズも続きました。
――改めて今後の抱負を
木下:
ジャイロの分野で、多摩川精機の知名度や実績は上がっていると自負しています。TAG320は世界にも通用すると自信を持って売り出せる商品です。
車載搭載品に求められる品質規格も満たしており、多くの商談が舞い込み、販路も広がっています。
慣性計測の世界は、陸海空で動くもの全てが対象であり、この分野で必要とされる自動運転や自律航法、自動制御について、ジャイロ技術をもってさらなる高みを目指したいと考えています。
また、光ファイバージャイロを民生品にも入れていきたいですね。鉱山用ダンプにはすでに何百台と納品していますが、そうした更新需要にも対応していきたいと思います。
萩本康夫会長もよく言われることですが、人にとって衣食住は欠かせません。
不足する人手を補うため、農機や建機の自動運転などへの期待は高まっており、それらに搭載されるIMUはますます重要で欠かせないものになるはずです。
